強み、使えてますでしょうか?
前回のニュースレターでは、「仕事で強みを生かすとイイコトあるぜ!」って話を展開したわけですが、それは氷山の一角に過ぎず。仕事がうまくいくなんてのは、強み活用のほんの序章に過ぎないんですよ。
| 🤝『Give & Take』のその先へ:与える人が勝つ時代【2025年版】 |
|
||
|
実際、自分の強みをちゃんと把握して、日常生活で意識して使っていくと、文字通り人生が変わるレベルの恩恵があるってことが、いろんな研究で示されてるんですよね。
- 幸福感やウェルビーイングがブチ上がる:
ペンシルバニア大学のセリグマン先生たちの有名な介入研究では、オンラインで自分の強み診断を受けて、上位5つの強みをフィードバックしてもらった後、「その強みの1つを毎日新しい方法で使ってみてね!」って課題をたった1週間やっただけで、幸福度が有意に上昇。しかも抑うつ症状が半年も減ったと報告されている。日本でも、大学生778名を対象にした調査で、「自分は結構幸せですねー」って自己評価してる人ほど、「VIA強み尺度」の点数が高いという相関がみられた - レジリエンス(逆境からの回復力)も強化される:
強みは、いわば心の緩衝材、ストレスに対するエアバッグみたいなもので、心理的なタフさを育ててくれる。自分の得意なことを意識してると、「まあ、なんとかなるっしょ!」って感じで、困難にぶち当たっても、それを乗り越える力があるって思えるようになる。結果として、ストレスにも強くなる。実際、Niemiec先生の2019年のレビュー論文によると、人間が持つ24種類の性格的な強みの全部が、何らかの形でレジリエンスと関連していると報告されている。特に、「自分らしさ」を体現するような「シグネチャーストレングス」を持ってる人は、落ち込みにくくて、回復も早い - モチベーションや自己効力感も爆上がり:
アメリカのギャラップ社が大学生を対象に行った研究では、自分の強みについてフィードバックを受けた学生は、自己効力感、自信、楽観性、さらには人生の目的意識まで有意に向上した。自分の強みを知るってことは、「自分にはこんなに価値のある特性があるんだ!」っていうポジティブな自己認識につながる。それが、「よっしゃ、新しいことやったるで!」という意欲や学習モチベーションを高めてくれる。 - 仕事や勉強へのエンゲージメント(没頭したり熱意を注いだりする度合い)も高まる:
自分の強みを仕事や学習で発揮できてる人ほど、物事に対して「うぉー!やったるぞー!」って感じで熱くのめり込める。ある職場のレビューでは、強みの活用は仕事の満足度、従業員のエンゲージメント、主観的な幸福感、さらには仕事のパフォーマンス向上と関連してるとまとめられている。企業が「社員の強みを活かそうぜ!」っていう取り組み(Strengths-Based Developmentって言うらしい)を進めると、離職率が下がったり、生産性が上がったりする可能性も指摘されてて、組織心理学的に見てもメリットが多い。 - 人生全体の満足度も向上する:
どんな強みを持ってるかによって、人生「まあまあ満足してるわー」って感覚に差が出る。国際的な調査では、「希望」「活力(熱意)」「感謝」「愛」といった強みを持ってる人ほど、生活への満足度が一貫して高い。これらは「心の強み(ストレングス・オブ・ハート)」なんて呼ばれたりもして、人とうまくやったり、前向きに人生を捉えたりする資質ほど、幸福感に直結しやすい。逆に、「学習欲」とか「好奇心」みたいな知識系の強みは、幸福との相関がちょい低い傾向がある(別に知識系の強みがダメってわけじゃなくて、幸福に直結しやすいのは感情系の強みだよ、ってこと)
と、まあ、ここまで強みのメリットを羅列したわけですが、ここで一つ、大きな問題にぶち当たるわけです。「いや、そもそも自分の強みって何なん?そんなん言われても、ピンとこないんですけど…」。そう、これなんですよ。自分の強みって、意外と自分じゃ気づきにくい。灯台下暗し、みたいなもんなんですよね。
そこで、「じゃあ、客観的に診断してもらおうじゃないか!」ってことで、世の中にはいろんな強みテストが開発されてるわけです。しかし、ここにもまた、一筋縄ではいかない落とし穴が潜んでいる。既存のテストって、いろいろと「うーん…」ってポイントがあるんですよね。性格テストでも似たような問題はよく指摘されてますが、強みテストも似たような問題を抱えてるわけです。
- 「長すぎて、やってらんねーよ!」問題:
精度の高さで知られる有名な強みテスト「VIA-IS」なんかは、回答項目がなんと240問もある。途中で「もう、ええわ…」って飽きちゃったり、集中力が切れてテキトーに答えちゃったりするリスクが大きい。 - 「短すぎて、これで本当に分かんの?」問題:
逆に、質問をめちゃくちゃ簡略化したバージョンもあって、中にはほんの十数問とかで強みを測ろうとするものもある。手軽なのはいいんだけど、質問数が少ないってことは、それだけ詳細な分析とか信頼性が犠牲になる傾向があるのもまた事実。帯に短し襷に長し、みたいな感じ - 翻訳、それで大丈夫そ?」問題:
多くの強みテストは、もともと欧米で開発されたものを日本語に翻訳してるわけだが、言葉のニュアンスは文化によって全然違う。直訳しただけじゃ、本来の意味合いがちゃんと伝わらなかったり、日本の文化背景にそぐわない質問になっちゃったりすることがある(例えば、欧米の「リーダーシップ」と日本の「リーダーシップ」は、求められるものが微妙に違ったりする)。そういう細かいニュアンスが抜け落ちちゃうと、せっかくのテストも精度がガタ落ちする可能性がある - 「そもそも、そのテスト、信頼できるの?」問題:
MBTIが科学的な検証をちゃんとクリアしてない、みたいな感じで、強みテストでも「これ、大丈夫か…?」って首を傾げたくなるようなものも残念ながら存在する。一方で、科学的にガッツリ裏付けられてるガチなテストは、専門家しか使えなかったりして、一般の人が手軽にアクセスできないというジレンマもある。
「じゃあ、どうすりゃいいのさ!?」って声が聞こえてきそうですが、阪大などの研究チームが日本人向けに「CST24(Character Strength Test-24)」なるものを開発してくれていて、これがかなり使えそうだったので今回はこいつをシェア。論文のタイトルにもある通り、24問の質問に回答する中で、強みが結構高い精度で見つけられるんじゃない?というんですな。
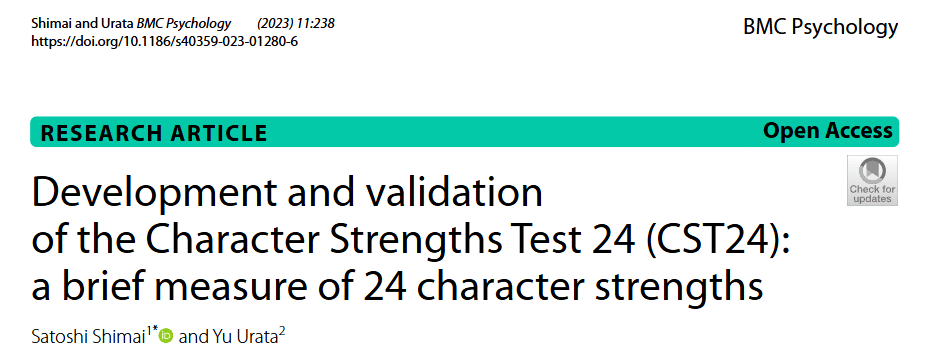
質問数が少なく手軽であることに加えて、このテストの特にうれしいのは、「翻訳、それで大丈夫そ?」問題に対する一つのアンサーになってる点。欧米で開発された尺度をただ日本語に置き換えるだけじゃ、文化的なニュアンスの違いで「なんかコレジャナイ感」が出ちゃうことがあるってのは先述の通り。その点CST24はVIAみたいな世界的に認められてる普遍的な強みのモデルをベースにしつつも、日本の専門家が、日本の文化の中で「ゼロから」項目を作ったんだそう。しかも、項目作成の段階から母語である日本語を使って、実際に日本の人たちで検証を重ねてるのはありがたいっすね。
さらに、信頼性の面でもかなり使えるんじゃないかなーと思ってまして、
- 内的整合性 (Internal Consistency):
24項目全部のクロンバックα係数が0.953だった。 α係数ってのは、0.8以上あれば「まあまあ信頼できるね」、0.9以上なら「かなり信頼できるじゃん!」って言われるもんで、0.953は相当高い。要するに、24個の質問が、ちゃんとそれぞれ異なる強みを測りつつも、全体として「強み」っていう大きな括りを捉えようとしてると評価できる。 - 再テスト信頼性 (Test-Retest Reliability):
424人の大人に30日後に同じテストに答えてもらったところ、24の強みのうち19個で、相関係数が0.5以上だった 。完璧じゃないけど、1ヶ月経っても大きく結果がブレるわけじゃないってのは、なかなかよいんじゃないでしょうか。
ってことが示されてます。つまり、CST24は「ちゃんと測れてるっぽいし、時間をおいても結果が安定してるっぽい」ってことがうかがえるわけです。
さらに「ちゃんと狙ったものを測れてるか?」っていう妥当性についても、しっかり検証されてまして、
- 収束的妥当性・構成概念妥当性 (Convergent & Construct Validity):
CST24の24個の強みのスコアが、主観的幸福感(SHS)、人生の意味(MLQ-p)、強みの知識(SKS)、強みの活用(SUS)といった、ポジティブ心理学の重要指標と、軒並み有意な正の相関を示した - 例えば、「希望」の強みが高い人ほど幸福感が高かったり(SHSとの相関0.526)、「活力」が高い人ほど人生の意味を感じていたり(MLQ-pとの相関0.580)した 。
- さらに、「ポジティブな自己への思いやり(Positive Self-Compassion)」とは正の相関、「ネガティブな自己への思いやり(Negative Self-Compassion)」とは負の相関があったってのも、CST24がちゃんと「良い感じの心の状態」と結びついてることを示している
って感じ。もちろんCST24は24個の強みをそれぞれ1項目だけで測ってるんで、そりゃあ240項目もあるVIA-ISみたいな大規模なテストに比べたら、精密さでは劣る、といった限界はありつつも、自分の強みを手軽に知るためのツールとして、試してみる価値はあるんじゃないでしょうか。また、高校生から社会人まで幅広い層でテストの性能が確認されてるってのも心強いですしね。
本ニュースレターでは、徹底的に調べあげたエビデンスをベースに「より信頼でき、真に価値ある情報」をレポートし、ゴミがあふれるネット上においてキラリと光る質の高いコンテンツをお届けすることを目指しています。あなたの人生を彩るヒントとしてご活用いただければ幸いです。
CST24を試してみよう!
前置きが長くなりましたが、それではCST24を試してみましょう。以下の強みの説明の文章を読んで、自分にどのくらいそういうところがあるかを考えてその程度を7段階で回答してください。
- まったくあてはまらない:1
- ほとんどあてはまらない:2
- あまりあてはまらない:3
- どちらともいえない:4
- 少しあてはまる:5
- だいたいあてはまる:6
- 非常によくあてはまる:7
- 独創性:わたしは、新しい見方や考え方を思いつき、独自の方法で解決につなげます
- 好奇心:わたしは、新しいものが好きで、新しい人と出会ったり、新しい経験をしたいと思っています
- 判断力:わたしは、ものごとをいろいろな側面から検討し、よく吟味した根拠をもって結論を下します
- 向学心:わたしは、自分の知識や経験を深めたいと考えて、新しいことを学ぼうと熱心に努力します
- 見通し:わたしは、ものごとのの流れや大筋をよくとらえていて、他の人から相談されることも多いです
- 勇気:わたしは、さまざまな困難を真正面からとらえ、怖がったりしりごみしないで挑戦します
- 勤勉性:わたしは、障害があったとしても、やり始めたことを完成するまでやり続けることができます
- 正直:わたしは、まじめで信頼されており、どんなときにも嘘をつくことはありません
- 熱意:わたしは、人生と日常生活に熱心で、いつも全力でエネルギッシュに活動します
- 親密性:わたしは、温かくて他の人に寄り添うことのでき、他の人からも好かれています
- 親切心:わたしは、他の人の面倒をみてあげて、何かしてあげたいという気持ちに満ち溢れています
- 社会的知能:わたしは、その場の流れや人の気持ちによく気がつき、先回りして行動することができます
- 忠誠心:わたしは、グループのメンバーと協力して、チームのために働き、積極的に責任を果たします
- 公平性:わたしは、平等に機会があることが大切だと思い、みんなに同じように接します
- リーダーシップ:わたしは、誰かに従うより、自分がリ-ダーとしてみんなのために働くのが得意です
- 寛容性:わたしは、理不尽な扱いを受け流すことができ、他人の失敗を許すことができます
- 謙虚:わたしは、自分の足りないところを認め、自分よりも他の人の成功を喜ぶほうです
- 思慮深さ:わたしは、あとで後悔しないように、慎重に計画し、十分に注意深く準備します
- 自己制御:わたしは、とても自制心があり、自分の感情や行動をコントロールして、平静で落ち着いています
- 審美心:わたしは、美しいものや素晴らしいものを見つけて、それに心打たれて感激することが多いです
- 感謝心:わたしは、人生の良い出来事を当たり前とは思わず、ありがたく感じその気持ちを伝えます
- 希望:わたしは、望みがかなうことを期待し、それを信じて楽しく励むことができます
- ユーモア:わたしは、人を笑わせるのが好きで、落ち込んだ雰囲気をなごませて楽しくすることができます
- 精神性:わたしは、人生には大切な意味があると信じており、それに従って行動します
採点方法:
採点方法は至ってシンプルで、それぞれの質問に対して、あなたが選んだ点数(1点~7点)がそのまま、その強みのスコアになります。特にややこしい計算や反転項目はないのでご安心を。
で、気になるのは「自分の点数って、他の人と比べてどうなのよ?」ってとこでしょう。論文によると、平均点はこんな感じだったみたいです。
- 大人846人の場合 (研究1):
- 平均点が一番低かったのは「正直」(3.61点)
- 平均点が一番高かったのは「自己制御」(4.55点)
- ほとんどの強みが3点台後半から4点台前半に収まってる感じ
- 高校生1098人の場合 (研究2):
- 平均点が低めなのは「勇気」(3.88点)
- 平均点が高めなのは「審美心」(4.72点)
- 大学生1101人の場合 (研究2):
- 平均点が低めなのは「リーダーシップ」(3.72点)
- 平均点が高めなのは「審美心」(4.75点)
まあ、当然ながらこれらの平均点は、あくまで参考程度。そもそも強みってのは、他人と比べてどうこうっていうより、自分の中で何が際立っているかが重要ですからね。
自分の「シグネチャーストレングス」を見つけよう!
論文に書いてある小難しい話は一旦ここまで。せっかくなので、以降は「で、この結果、どうやって使ったらええのん?」って点について、私の独断と偏見も交えつつ、実践的な活用法を考えてみましょう。
まず、おすすめしたいのは、あなたの得点が高かった上位5つ程度の強みに注目すること。これらが、いわゆるあなたの「シグネチャーストレングス(Signature Strengths)」に当たるわけです。
このシグネチャーストレングスこそが、あなたが意識して使うことで、日々の幸福感が高まったり、仕事やプライベートで物事がスムーズに進んだりする、いわばあなたの「必殺技」みたいなもんなんですよ。冒頭でも触れた通り、ポジティブ心理学のドン、セリグマン先生の研究でも、「自分の強みのどれか一つを、毎日新しい方法で使ってみる」っていう、たったそれだけの課題を1週間やっただけで、幸福度がグンと上がって、抑うつ気分が半年も続いたってことも報告されています。まさに、強みを使うってのは、それくらいパワフルなんですわな。
ここで、「えー、でも点数が低かった強みはどうすんの? 弱みはやっぱり克服しなきゃダメなんじゃないの?」って真面目なあなたは思うかもしれません。その気持ちもよく分かります。私たちはどうしても「できないこと」に目が行きがちですからね。
しかし、実は、「弱みを直せば幸福になれる」ってわけでもないってことが、いろんな研究で示唆されてたりするんですよ。それどころか、弱点をチマチマ修正したところで、個人とか組織のパフォーマンスはたいして変わらんかったりするという、ちょっと残念な報告もあるくらいなんですよ。
もちろん、場合によっては、最低限のレベルまで引き上げる必要はあるでしょう。しかし、強みは、あなたが元々持ってる強力なエンジンみたいなもの。それを使わずに、苦手なことを克服しようとアクセル踏んでも、なかなか前に進まない。それどころか、強みも、無意識のままだと宝の持ち腐れになっちゃうことが多い。自分では当たり前にできてるから、それが「強み」だと気づいてない。結果、弱みばっかり意識して、それをなんとかしようと四苦八苦した結果、どうなるか? よくても「平均的な人間」に落ち着いてしまうでしょう。
これはあくまで私の個人的な意見ですが、「平均的な人間に落ち着く」ってのはかなりつまらない。だって、面白くないじゃないですか。みんなと同じようなこと考えて、同じような行動して、それで得られるもんなんて、たかが知れてる。
ちょっと話がぶっ飛びますけど、経営論者の楠木健さんがAIについて面白いことをおっしゃってたんで、ここで紹介させてください。
生成的なものであろうとなかろうと、これからも変わらないであろうAIの本質は(極めてカバレッジが広い)前例主義にあります。 AIから出てくる知見は多数派の最大公約数的なものへと流れていく傾向にあります。 つまりはAIを利用すればするほど平均へと回帰していくことになります。
僕が専門としている競争戦略にせよアクティブ運用にせよ、最大の敵は平均回帰です。他の人と違った景色が見える。他社ができないこと・やらないことをする。ここに戦略の本質があります。
ということは、ジェレミア氏が言うように、経営判断におけるAIの利用が進むほど、人々は画一的な考えに傾むくということになります。その結果として、平均回帰からフリーな独自の視点を持つ人の競争優位はますます大きくなる。
同じことを繰り返していくオペレーションの改善にとってAIの活用は極めて有用です。ただし戦略的な洞察や意思決定はオペレーションとは違った次元にあります。僕は企業の競争戦略についてのアドバイスをすることを仕事の一つとしておりますが、 AIは脅威にならないと考えています。
これは私的に結構シビれた話で、 AIがどれだけ進化しても、結局は「前例」の膨大なデータから最適解っぽいものを探してくる。つまり、多数派の、平均的な考え方に近づいていくってこと。そんな中で本当に価値があるのは、その他大勢とは違う、独自の視点や発想。楠木さんは企業の競争戦略の話をされてますけど、これって私たち一人ひとりがどんな人生を送るかっていう個人の戦略においても、めちゃくちゃ共通すると思うんですよね。みんなが「平均」を目指してる中で、自分の「強み」というユニークな武器を磨いて、他とは違う景色を見る。これこそが、これからの時代を面白く生き抜くコツなんじゃないかなー、と。
と、だいぶ話が逸れましたが、要は、点数が低かった「弱み」に過剰に囚われる必要はないってこと。それよりも、あなたのシグネチャーストレングスをどう活かすかにエネルギーを注ぐ方が賢明じゃないかと。
もちろん、テストの結果を見て「うーん、この強みがトップに来るのは意外だな…」とか「これはもっと高いと思ってたのに…」なんてこともあるでしょう。それで全く問題なし。何度も言うようですが、このテストは、絶対的なあなたを診断するものじゃなくて、あくまで自己理解を深めるためのツールの一つ。結果をきっかけに、「確かに、言われてみれば私にはこういう面もあるかもな」とか「この強み、もっと意識して使ってみようかな」みたいに、自分と対話する時間を持つことが、何よりも大切ってわけですね。
私自身も、昔VIA-IS(例の240問あるやつ)をやったとき、「ユーモア」とか「好奇心」が上位に来たのは「まあ、せやろな」と納得だったんですけど、「愛情」とか「親切心」も意外と高くて、「おっ、俺って意外とイイ奴じゃん?」って思った記憶があります(笑)。それ以降、これらのポイントを意識して、例えば、家族や友人とのコミュニケーションで、ちょっと大げさなくらい感謝の言葉を口に出してみるとか、仕事で後輩が困ってたら、自分の作業を一旦止めてでも相談に乗って、一緒に解決策を考えるようにしてみたりしてますね。まあ、できてるかどうかは別として、意識するだけでもだいぶ違う気がします(少なくとも心理状態はかなり改善されているように感じます)。
大事なのは、点数に一喜一憂することじゃなくて、自分の強みの「傾向」を掴んで、それをどうやって日々の生活で「活用」していくかを考えること。
例えば、もし「向学心」があなたのシグネチャーストレングスの一つだったら、毎日15分でもいいから新しいことを学ぶ時間を作ってみるとか、仕事で新しいスキルを習得するオンライン講座に申し込んでみるとか。もし「親切心」が高かったら、近所のゴミ拾いに参加してみるとか、困っている様子の同僚に「何か手伝えることある?」って声をかけてみるとか。
そんな風に、自分の強みを意識して行動に移していくことで、きっと人生はもっと豊かで、もっとあなたらしく、面白いものになっていくはずです。
以上、あなたのシグネチャーストレングスは何でしたか? それをどう活かせそうですか? CST24をヒントに、あなた自身の強みを最大限引き出せる、最強の「自分のトリセツ」を作ってみてください!
ってことで今回はこのへんで。ではまた!
「強み」周りのおすすめ本
1.ポジティブ心理学が教えてくれる「ほんものの幸せ」の見つけ方 ──とっておきの強みを生かす (フェニックスシリーズ No. 118)

ポジティブ心理学の創始者セリグマン先生自らが、強みとは何か、そしてそれをどう活かせば「ほんものの幸せ」に繋がるのかを分かりやすく解説してくれている、まさに強み理解の入門にして決定版。
2.強みの育て方 「24の性格」診断であなたの人生を取り戻す
VIA研究所の教育ディレクターであるニーミック博士らが、24の性格の強みそれぞれについて、その特徴、なぜ重要なのか、そしてどうすればその強みを日常生活や仕事、人間関係で具体的に活かせるのかを、めちゃくちゃ丁寧に解説してくれている実践的なガイドブック。
3.さあ、才能(じぶん)に目覚めよう 最新版 ストレングス・ファインダー2.0
こちらはVIAの24の強みとは少し毛色が違いますが、ギャラップ社が開発した「ストレングス・ファインダー」を使って、個人の「才能(繰り返し現れる思考、感情、行動のパターン)」を見つけることに特化しており、その才能をどう強みに変えていくかのヒントが満載。
経験が無駄というわけではないが、経験がないルーキーに特有の思考と行動は多くの場面で大きな強みになる。そしてそんな「ルーキー・スマート」は決して新人の専売特許ではなく、ライフステージのどこにいる人でも(努力次第で)身に着けることが可能。現代社会を生き抜く上でこれを体得しない手はない pic.twitter.com/rADpOhCQ70— おくさん/OKUSUN🇯🇵🇨🇳 (@Astella6174) June 21, 2022

おくさん/OKUSUN🇯🇵🇨🇳 @Astella6174
まだ若手だし強みなんておこがましい。。って方にはこれ。「経験がない」が大きな強みとなりうるのだ!って考え方が腹落ちするはず(若手以外にも使える考え方であるのがさらに面白い)。

